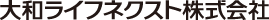2022年4月から中小企業にも「パワハラ防止法」が義務化されています。
いわゆるパワハラやセクハラは、職場におけるもっとも深刻なストレス要因のひとつであり、男女雇用機会均等法やパワハラ防止法に基づき、企業が対策をしておくことが強く求められています。
そもそも、パワハラにはどのような種類があるのでしょうか?一度整理をしてみましょう。
厚生労働省の資料ではパワハラに該当する行為と、該当しないと考えられる行為を挙げています。
出典:職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
《身体的な攻撃》
殴る、蹴るなどの暴力に代表されるハラスメントです。
また物を投げるなど、身体的に危害を及ぼすような行為もハラスメントに該当します。ただし、誤ってぶつかった場合などは対象外です。
《精神的な攻撃》
主に言葉の暴力などにより人格を否定したり、恫喝したりするようなハラスメントです。
大声での威圧的な指導なども含まれます。また能力を否定し、罵倒するような内容のメールを当該相手を含む複数の従業員宛に送信することもハラスメントです。ただし、度々注意しても改善しない場合に直接強く指導することは該当しない場合もあります。
《人間関係からの切り離し》
自身の意に沿わない特定の個人を部屋に隔離したり、意図的に業務連絡をしないことで孤立させようとしたりするハラスメントです。
業務上の必要性や、育成のため短期的に別室で研修等の教育を実施したり、感染対策の一環から部屋を切り離すといった行為は該当しません。
《過大な要求》
担当者に必要なレクチャーを行わないまま、担当者が対応できない負荷の業務を要求するハラスメントです。
また、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制することもハラスメントです。判断については難しいところですが、厚生労働省の指針によると育成のために少しレベルの高い業務を任せることは該当しません。
《過小な要求》
過小な要求は、主に退職させたい従業員に対して、単純な作業を長時間させる、業務を与えないといったハラスメントです。従業員の能力や事情に応じて業務量を軽減することなどは該当しません。
《個の侵害》
個の侵害は、業務上必要のない従業員のプライバシーに関する情報の提出要求や、それを強要するハラスメントです。
職場における個人情報の暴露なども含まれます。体調の優れない従業員に対し、家族の状況をヒアリングすることなどは該当しません。
日ごろからハラスメントが発生しないような職場環境を整えておくことが重要ですが、もし事案が発生してしまいパワハラと認定された際には、加害従業員だけでなく企業も責任を問われる可能性があり、具体的には「不法行為責任」と「債務不履行責任」の2つがあります。
不法行為責任においては、使用者責任(民法715条)が争点になります。
特にパワハラの場合には「業務の執行につき」の要件を満たすことが多いことが考えられ、その場合には使用者である会社も損害賠償責任を負い、その範囲は加害者本人と同じものとなります。
もうひとつの債務不履行責任とは、会社の責務である安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)を負わせるという考え方です。
会社は従業員との雇用契約において、適切な就業環境を提供すべき義務を負います。それにもかかわらず、パワハラ問題を放置して従業員がメンタルヘルス疾患を発症してしまった場合には、労働者の利益が不当に侵害されないよう配慮する義務を怠ったとして、債務不履行責任が発生します。
そのような事案の発生を防止するために、企業ではハラスメント相談窓口の設置や社内研修の実施が必須となりますが、それでも万が一事案が発生してしまった際の対策として、それらの対応に掛かる費用を保険で備えておくことをおすすめします。
詳しい資料をご用意しておりますので、ご関心があればお気軽にインシュアランスエスコート部までお問い合わせください。
大和ライフネクストでは、ご加入の火災保険の無料診断サービスを実施しています。
火災保険の無料診断サービス希望の方は下記お問い合わせフォームをクリックしてください。
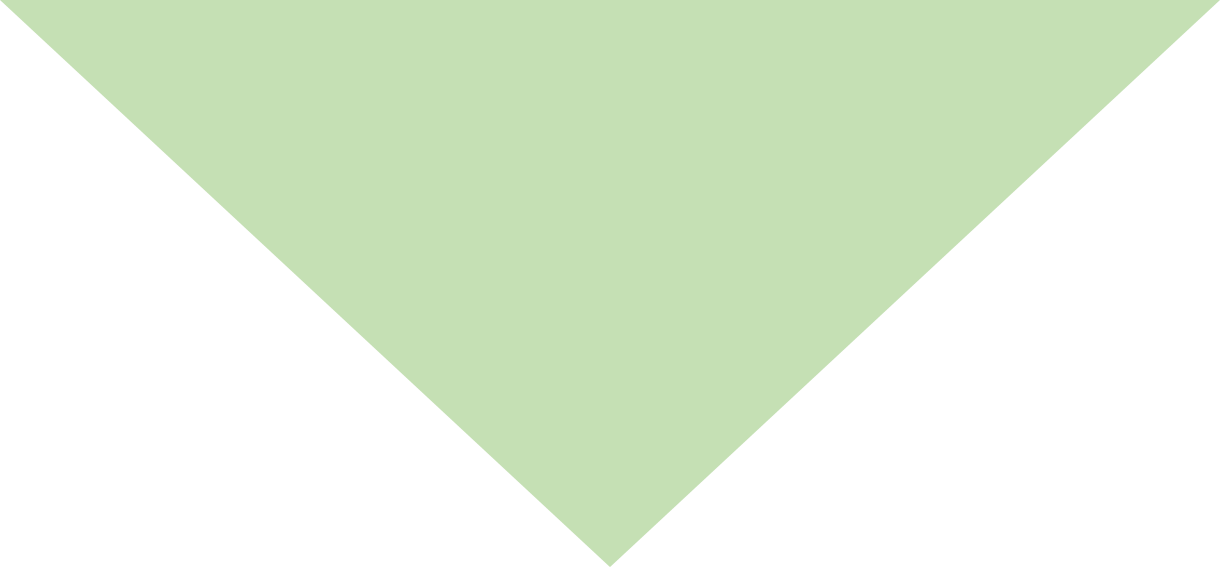
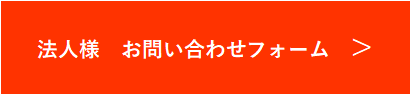
企業向け保険情報メールマガジンをご希望の方はこちらよりご登録ください。

新着情報・セミナー情報
2024.07.29