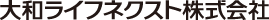火災事故は、冬場の乾燥に伴い12月頃から増え始め、3月に件数のピークを迎えます。
(消防庁統計資料より)
毎年11月には、消防庁が「秋季全国火災予防運動」を実施しており、冬場に増加する火災事故の予防や火災による死者(一酸化炭素中毒等も含む)の減少を目的に行っています。
(2022年は11月9日~11月15日まで実施)
「秋季全国火災予防運動」は、主に住宅火災の予防に関する内容ですが、バックヤードなど死角になりやすい箇所の巡回強化といった、企業にも有効な対策が紹介されています。
ご参考にしていただき、ぜひ火災予防にお役立てください。
【秋季全国火災予防運動URL】
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/prevention001.html(消防庁ホームページより)
企業火災と住宅火災の大きな違いに、「危険物・可燃物を取り扱う事業の存在」「被害額が高額になりやすい」が挙げられます。
危険物・可燃物を取り扱う企業では、「火災発生の可能性がある箇所の特定」や「製造場所付近の可燃物有無の確認」「バックヤードなど死角になりやすい箇所の確認」等が事前対策として有効であり、その箇所の防火対策をすることで被害の拡大防止に役立つと考えられます。
一方で、危険物を置いてある可能性が低い事務所などに関しては、確認不要と思われがちです。しかし、喫煙所・電気室など、火気や電気の管理が必要な箇所は一定数存在するため、着火・延焼等の確認は必要です。
併せて、消火器・スプリンクラー等の定期的な点検や、使用方法を確認しておくことも重要です。
火災対策の事前準備・確認が完了しましたら、次は対応策を検討しましょう。
具体的には、下記のような点が挙げられます。
《指揮系統の整備》
一定の収容人数・床面積を持つ建物には、防火管理者選任が法律で定められています。
また、規定要件にあてはまらなくても防災対策指揮系統を整備し、万が一に備えた対策チーム・組織構築が望ましいといえます。
《防災計画・マニュアル作成》
防災対策チーム・組織等が行うものに、「火災発生時の役割分担」「避難経路の確保」「初期消火活動のやり方」など、防災計画・マニュアル作成があります。
火災原因となりうる可燃物・設備等の取り扱いや、火器等の使用ルールを定めておけば、火災リスク軽減につながります。
《BCP策定》
事業継続・早期復旧を実現するためには、BCP策定が有効です。
BCPの有効性につきましては、企業の地震対策とBCP(事業継続計画)でご紹介しておりますのでご参考までにぜひご覧ください。
防災計画・マニュアルを作成済みであっても、想定通りに対応できるとは限りません。
特に事務所・工場など、多くの社員がいる場所では混乱に陥る可能性もあります。
そこで、定期的に避難訓練を実施し、有事発生時の行動について周知徹底を行うことが必要です。
併せて初期消火訓練を行えば、被害拡大防止にも役立ちます。
火災事故に関して、発生の事前予測は難しいですが、その原因は何らかの形で存在します。
原因となる部分を見落とすことで、災害発生の危険性や被害拡大のリスクが高まります。
消火器・スプリンクラーなどの定期点検のほかに注意を払うべき点として、例えばOA機器の普及によるコンセント数の増加により、トラッキング現象(※)の危険性がある箇所が増加しているといえます。
火災が想定しうる原因の日常的な確認・点検はとても重要です。
※トラッキング現象とは、コンセントを長期間差し込んだ状態にしておくと、コンセントと差込口のわずかな隙間に埃等が付着し、その埃等が湿気を帯び通電することで差込口から発火する現象のこと
火災による防災対策は、火災発生防止であると同時に、早期復旧に向けた対策でもあります。
代替生産設備の確保、クラウドサービス活用など、1日でも早い事業再開に向けた計画・BCP策定が重要です。
冬場に向け、改めて防災対策を見直してみてはいかがでしょうか。
大和ライフネクストでは、ご加入の火災保険の無料診断サービスを実施しています。
火災保険の無料診断サービス希望の方は下記お問い合わせフォームをクリックしてください。
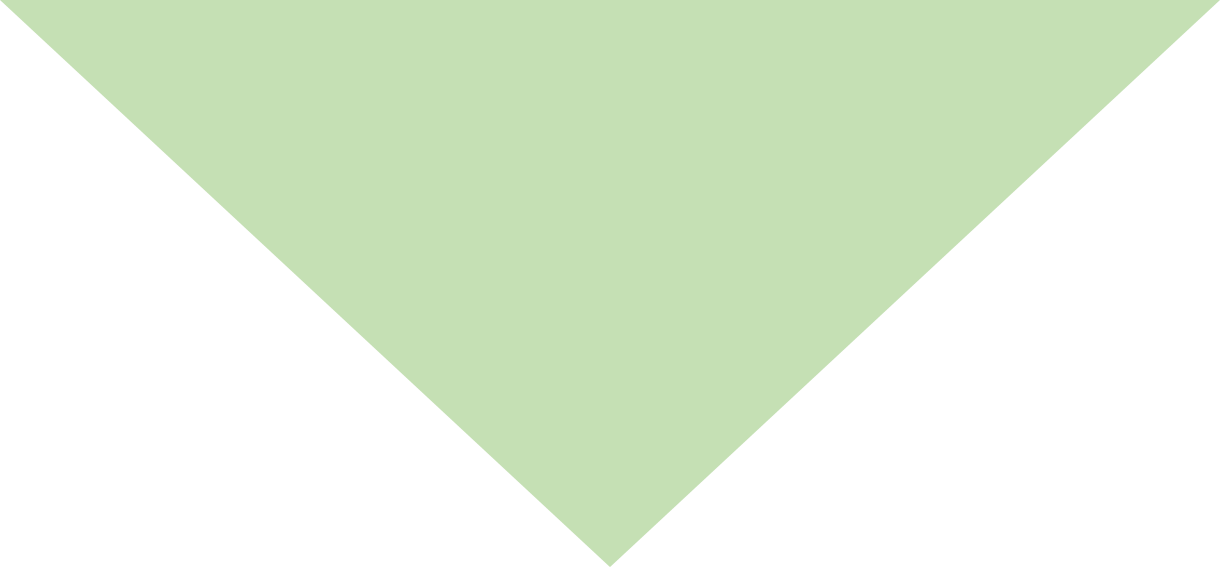
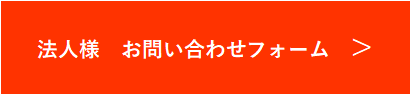
企業向け保険情報メールマガジンをご希望の方はこちらよりご登録ください。

新着情報・セミナー情報
2022.12.01